マネジメント
寄りそうこころの一年に
新年度の計画を発表する時期になりました。
新年度を考えるのは楽しみでもあり、言葉にするエネルギーがいるので、少し心が重い時期でもあります。
私は自分がいつかこの病院を離れて後継者につないでいくことについて、考えています。
組織の存続を線で引いてみて、ご縁とタイミングがあってここにいるんだとよく思います。
A地点からB地点まで。そのあとは別な看護部長がバトンをもらってC地点へ。
駅伝のようにたすきをつないで組織が続いていく。
同じ路線を継承するのがいいのか、旧来にとらわれず斬新なアイデアで新しい風を吹かせるのか。
いろんな妄想をしつつ、私なりに次世代を担うマネージャーを育てているつもりです。
時代の流れに合わせて、変化しながら組織が続いていくってすごいことです。
失敗や成功を積み重ねながら、去年より今年、昨日より今日へとつながってきたんですから。
新年度の病院の目標が「寄りそう」に決まりました。
寄りそうということ。
寄りそわせていただくには、そもそも信頼関係が必要でして。
傍らに座って共に時間を過ごすこと。
患者さんのそばに寄りそっている職員に「いいケアをしているね」と応援すること。
ゆっくりそばにいられなくとも、ほんの数分でもしっかりそばにいること。
やさしく背中や手足に触れること。
ハグすること。
そばにいなくても心で寄りそい、想いをはせること。
その人の人生を大事に思うこと。
私が「寄りそう」という言葉から連想するのはこんな情景です。
少しできているところもあるんだけど、もっとみんながこのことを大事なケアだと思って実践するにはどうしたらよいか、ディスカッションがいるなあと思いました。
そこで先日の師長会で、今年度の振り返りとともに、新年度取り組むことは何か、「寄りそう」という言葉をどう解釈し、私たちの定義にするかを話し合いました。
みんなでブレーン・ストーミングを約1時間半。
日ごろから何を言ってもいい風土なので、書くのが間に合わないくらいみんなから言葉が飛び交いました。
そして「寄りそう」という言葉については、患者さんやご家族さんはもちろん、共に働く仲間に対しても寄りそい思いあう風土にしたい。
一人がみんなのために、みんなが一人のために、それを実現させたいね、という話になりました。
そして最終的に看護部の目標は「寄りそうこころ」に決まりました。
寄りそうこころを持った看護師を育てましょう。
寄りそうこころでケアしましょう。
寄りそってお互いにおもいやりましょう。
「こころ」に、そんな思いが込められました。
魂が、入ったなと思う瞬間です。
今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
昼寝をしてると傍らにオカメインコが寄りそってくれています。
2029年からの手紙
2019年札幌南徳洲会病院の新病院建設会議に参加されている皆さんへ
2029年1月5日の今日、私はカナダのイエローナイフというところに来ています。
雄大な自然の中のログハウスで、おいしいコーヒーをいただきながらこれを書いています。
私は昨年退職して海を渡り、昼間は食堂で働いて、夜はオーロラを眺める、夢のような生活をしています。
あの頃皆さんと一緒に新病院の建設を議論していたことを懐かしく思い出します。
あれから10年が経ち、四十坊院長の頭はすっかりロマンスグレーになりました。
相変わらず日ハムを応援するのを楽しみにしながら、今日も外来診察に出ています。
40名弱だったボランティアさんは今や200名を超え、職員より多いくらいです。
そのおかげで朝早くから夜遅くまで、あちらこちらでボランティアさんが見かけられます。連日のように音楽イベントが開かれ、朗読や傾聴、マッサージをしてくださっています。
1階の空間で、カフェを始めた元ボランティア・コーディネーターの鈴木さんが、おいしいコーヒーを淹れて、話術で笑わせてくれるので、お客さんがひっきりなしです。診察を受けに来た人もカフェにきたのかと勘違いするくらい、待ち時間を心地いい時間にしてくれています。
外にはアイスキャンドルが何十個も連なり、美しい光景が評判となって病院なのに見物客が増えました。
春からは菜園と果樹園の準備が始まります。桜の植樹も8回目となり、小さいけれど今年は桜並木の下でお茶会ができそうです。
あの頃はホスピスに研修生がよく来てくれてましたよね。
今は全国から院内のあらゆる部署に研修生が来てくださるようになりました。
外来も透析室も障がい者病棟も、よいケアを実践し続けてくれたからですね。
「入院するならこの病院」でトップテンに選ばれたのも皆さんのおかげです。
2018年に始めた緩和ケアセミナーやNPOホスピスのこころ研究所の活動が世に広まり、人生の最後の時をどう過ごすかを考える場として、私たちのケアを見に来る方が増えたのです。ありがたいことです。
前野総長は全国各地からお声がかかり、執筆や講演活動で忙しくなりましたが、楽しそうにしていますよ。下澤事務長は総長のスケジュール管理が結構大変そうですが、シュヴァービングの森をジョギングし、昆虫と戯れるのが癒しになっているようです。
今年は古民家を改修して、ホームケアクリニック札幌・藤原院長の念願だったホームホスピス「かあさんの家」を始めることになりました。病院ではなく、自宅でもなく、一人暮らしの方も安心して過ごし、穏やかな環境で旅立つことができる、そんな場所がいよいよ完成します。
今思うとあの頃、新しい病院についてみんなで話し合うのが一番楽しかったと思います。
そして前野先生がよくおっしゃってたように、その話し合ったプロセスがとても大事だったなって思います。建物が新しくなっても、そこに働く人の心が大事だから。
仲間を信じ、いつも目の前の患者さんにいいケアをしようと努力する、その小さな積み重ねが今につながっているのです。
今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
新年初出勤前日の夜、こんな妄想が膨らみ眠れなくなりました。
病院の「おまあ指数」を考える
ドラッカーの「マネジメント」を学ぶ読書会で、以前こんな話を聴きました。
ウナギ屋さんで会計するときにお客様から
「おいしかったよ」
「また来るね」
「ありがとう」
という言葉をかけていただいたら、それを紙に書いてカウントしていくそうです。
それらの頭文字をとって、「おまあ指数」と呼びます。
おまあ指数がお店の評価であると受け止めるのだそうです。
それらの言葉をいただけるように、店員さんが何をしたらいいかと考え、行動するそうです。
それ、すごくシンプルでいいなあ。
調理する人は一番いい状態で食べてもらおうと努力するし、
ホールの人は心地よい空間を整え、明るい笑顔でお迎えしよう、と思うでしょうし。
「こうしなさい」という上からの指示命令ではなく、
自らどうしたらお客様に喜んでもらえるかを考え行動する。
これこそが目標管理ですね。
何か病院でも応用できそう。
病院は「在院日数」「治療成績」「手術件数」「ベッド稼働率」という数値目標で測られることが多いけれども、
本当に患者さんのためになったのか、満足していただいたのか、についての指標が少なくて(いや、私がわかってないだけかもですが)、年に一度の患者満足度調査だけではあまり効果的ではないと感じています。
「ありがとう」
「ここへきて良かった」
「やさしい病院だね」
などと言っていただけるとうれしいな~~
「あこや指数」⁈
でもせっかくだから、これは師長さんたちと話し合う材料にしよう
今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
楽しく行動できるのがいいよね~
大丈夫。みんな一緒に頼むよ。
私はピーター・ドラッカーの本を使った読書会で、月に1度勉強しています。
もう5年くらいになるでしょうか。
読書会のメンバーは5~10人位で、異業種の集まりです。
それぞれが「経営者の条件」という本の、決まった章を事前に読んできて集まります。
読んだ中で自分が一番ぴんときた文章に線を引き、どうしてそこに線を引いたのかについて、話をします。
体験としていろいろ感じてはいても、いわゆる概念化できてない、コトバとしてうまくまとめられていないことがたくさんあるのですが、ドラッカーの本には「そうそう、それそれ!」って思うことがぴたっと明確に記されています。
一年かけて一冊の本を読んで話し合い、翌年また「まえがき」からスタートするのですが、まったく飽きることがなく、去年は引っかからなかったコトバに線を引くこともあれば、「やっぱりこの文章がすきだなあ」と思うこともあるし、まるで初めて読んだかのような新鮮さを味わうこともあります。
そして参加者はそれぞれ違う仕事をしていますが、悩む事柄は一緒だったりするので、自分の身に置き換えて考えることがとても勉強になります。

先日は、ある方が自分の率いるチームメンバーがみんなバラバラな方向を向いていて、同じ方向を向かせるにはどうしたらいいか、という話をされました。
それぞれは能力の高い人たちなのに、一緒に協力して一つのものを作り上げようという空気がなく、困っているという話でした。
それについて別の方が「リーダーが、”このチームはバラバラだ”と思っているといつまでもバラバラなんだよね。リーダー自身が”大丈夫。みんないっしょに頼むよ。”と思えばひとつになるんだ。”あなたの強みはこれこれだから、それを使ってね”と一人一人に伝えたらいいんだよ」と、柔らかにおっしゃいました。
そのコトバは私の体の中にするりと入ってきました。
自分の見方、思いひとつだなあと思うことは私もしばしばあります。
人の心や向き合い方を変えようと思うとうまくいかない、というのもよく経験してます。
「こうするべきだと思うからこうしてね」じゃなくて、
「私はこう思うんだよね。それを一緒にやってもらいたいんだ。手伝ってくれる?」という風に伝えたら、自分も楽に伝えられる気がします。
今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
スポーツみていてもそんな感じがする。青学とかカーリング娘とか。
坂本すがさんの講義を聴いてきました!
こんにちは。札幌南徳洲会病院の工藤です。
平成30年1月19日、サードレベル10期生の特別講義を聴講してきました。
サードの修了生は、何年経っても講義の聴講ができるのです。ウレシイ特典です。
特別講義は受講生の希望を聞いて、大学が調整してくれるのですが、今回の講師は日本看護協会前会長の坂本すがさんでした。
その話を知ったとき「すごーい!坂本すがさんを呼ぶなんて」と思いました。
私にとっては遠い雲の上の方です。
数年前、北海道看護協会の支部の仕事をしている間に2回ほど看護協会の総会に行ってきました。壇上でお話をする坂本会長のお話を聴きましたが、言葉の端はしに飾らない人柄が表れて、「この人が上司だったらどんな職場だろうなあ」と思ったものです。
特別講義では、ご自身の体験をベースにしながら、看護管理者とはどんな存在か、社会の変化について、将来に向けたビジョン、これからの管理者に期待することなどをユーモアたっぷりに語ってくださいました。
「人の話は本当にそうか?!と批判的に聞け」
「自分の内なる言葉で語れないと人は動かせない」
「自分の病院のことばっかりじゃなく、この地域はどうあるべきか考えていくリーダーが必要」
「50代からセカンドキャリアの準備を」
など、キーワードを一杯もらいました。
一番心に残ったのは、
「仕事は楽しくないと意味がない」という言葉です。
自分で問いを立てながら自分の考えを持ち、わくわくしながらアクションを起こし、人間力を鍛えろ、という続きにおっしゃったコトバでした。
そして読みたくなる本の話題もたくさんされたので、今年の課題図書にしようと思います。
今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
せっかく本も持っていたのに!サインもらいたかったな。
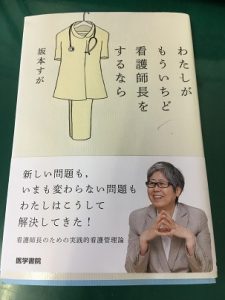
認定看護管理者サードレベルの実習生とのご縁
こんにちは。札幌南徳洲会病院の工藤です。
1月15日・16日の2日間、札幌市立大学で開講している認定看護管理者サードレベルの10期生がお二人、当院の実習に来られました。
こんな小さな病院に、ご縁をありがとうございます。
看護師もキャリアを積むうち、自分の専門性を高めたり、なんでもできるジェネラリストの方向に進んだり、ふと自分はどの方向に進むのか、キャリアを考えるときがあります。
「ずっとこの道でいいのか」「この病院(施設)で働き続けるか」
看護管理者も一人の人間なので、自分の不得意なことにコンプレックスを感じたり、この道でいいのかと悩み迷ったりします。
私はこのサードレベルの3期修了生です。
北海道の看護管理者研修はファーストレベル・セカンドレベルが北海道看護協会で行われ、サードだけが札幌市立大学で行われます。
大学に行ってない私は、大学という場所に身を置くことがうれしかったりしました。
そしてファースト・セカンドとは違ってサードは答えなき答えを見つける場所と言ったらいいでしょうか。禅問答のような質問が飛んできて、自分が何を持っていて何をどう考えているのか(考えていないのか)を突き付けられる場所でした。
目の前の事象だけに振り回されるな、そして小手先で解決しようとするなと教わった気がします。軸をしっかりと持ち、自分の思想を持ち、それを人に伝えて理想とする看護の場を実現するために、私は何をするのか。それを論理的に考える、トレーニングの場だったのです。
ちゃんと世の中のことを知ろうとしてなかったよな。
身の回りで起きていることを俯瞰して考えられてなかったよな。
そして知識のなさ、本をろくに読んでないこと、エトセトラ。
友が皆、我より偉く見える・・。
ガーンとなり、2期目が終わるころ(サードレベルは3期に分かれています)にはひどく落ち込みました。
でも仲間に支えられ、先生方の教えに導かれなんとか卒業できました。
遠くから来てくれた後輩たちには、私の知っていること、体験したことは、へなちょこで情けないことも含めてアウトプットできたと思います。
管理者も一人の人間。看護部長だからって完璧ってことはありえない。
生きてる限り、学びの途中なんだと割り切っていくしかない。
結局は自分の得意なことと周りの人の力を借りながら前に進むしかない。
彼らがどんな管理者になっていくのかな~
互いの話を聴き合いながら、私もたっぷりエネルギーをいただきました。
この人たちが日本の看護業界を変える人かも知れない、そう思うとワクワクするのです。
いやいや負けちゃいられません。私は日本一のいい病院創るつもりですよ!
今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
アウトプットは自分の振り返りになるね。

働かないアリにも意義がある
先日の看護学会で「働くアリと働かないアリの”ありよう”からみる個性と組織の存続」というテーマの講演を聞きました。
講師は北海道大学大学院農学研究院生物生態体系准教授の長谷川英祐先生でした。

なんで看護学会でアリの話??と思いながら聞いてみると・・
アリにも働くアリと働かないアリがいて、働くアリだけを集めてコロニー(巣)を作ると働かないアリが出てくるし、働かないアリだけを集めても働くアリが出てくるというお話でした。全員働けば仕事の効率がよくなってみんなで楽に暮らせるんじゃないかと思うのですが、全員で100%働けばいっぺんに疲れてしまう。誰かが疲れて停滞するときに、普段働かないアリが働くことで、組織が維持存続できるのだというのです。それは(こうなったとき働く、という)個別の「反応閾値」によって決まるそうです。
病院組織もそうかもしれません。
私が仕事をしてきたどの組織でも、常に隅々にアンテナを張って、きっちり仕事をする人と、一見休んでる(遊んでる)ようにみられる人とがいます。一日中走り回って仕事しているときに、のんきに宅配ピザの話をしている人がいると、私は「なんであの人はもっと働かないんだろう?」と腹を立てていました。
しかし、昨年自分が当院へ来てからは、私自身が「働かない人」になっているように思います。なぜかってここのルールや人間関係などが見えない間、ひと渡り見回したときの印象は、自立した看護集団だなと思ったからです。そうすると「私がやらねば」みたいな気持ちは霧散霧消して、内部環境をもっとよくするために、さて、次は何をしようかなと思える。あるいは外に向かって何かをしようと思える。
けれども、何か内部にピンチが起きたらば、いつでもなんでもするよ、という気持はある。できるかどうかは別としてね(笑)
これが働かないアリの気持ちにちょっと近いかも知れません。
だから、働かないアリがいるってことは少し余力があるっていうことじゃないかと思うのです。
転職してきた人もコロニーの違いを感じるだろうと思います。それまでのコロニーでは100%働いてきたけれども、別な場所へ行くとルールや人を覚えるまでは一時的に自分の能力は十分発揮できない状況になります。日々コロニーの状況を観察しながら、自分の働き方を探り、求められているのは何かを考える期間が必要です。何が得意なのかを理解され、適切な役割や目標を見つけたり与えられたりして、自分らしさを100%発揮できたら、「働かされてる」というのではなく、幸せに働く、ということになるのでしょうね。
この話をある人にしたところ、みんなが100%働いて「働かない奴はだめだ」みたいに目を光らせているよりは、「いざと言うときは頼むよ」というくらいのアソビがあった方が、きっと組織は長持ちするのだと思う、という風に言われました。
つまり私もあなたも認め合う組織になるってことが大事なんですね。
参考まで⇒https://www.athome-academy.jp/archive/biology/0000001082_all.html
今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
日々是感謝。

学ぶ楽しさを!看護管理研修
先日、道内グループ病院の師長を対象に、管理研修が行われました。
今年はこういう研修の企画者側にいます。
忙しい中、現場を部下に託して勉強に来るわけですから、最高に魅力的な研修を企画しなきゃね、と腕まくりして準備したのです。
私はイベントとか研修とかを考えるのが結構好きでして、参加者にどうやって楽しんでもらおうかなあとか、この講義がしみ込むにはどうしたらいいかなあとか、参加者がいかに体感できる研修にするかという視点で、いつも作ろうとしています。
院内研修は人材育成の場であり、顧客へのサービスでもありますから。

7月の研修は副主任を、9月は師長、11月は主任を対象にしています。
年度初めに北海道ブロック長と念入りに打ち合わせし、研修の目的・目標をしっかり作りました。
構造が明確だと、何をすべきかわかりやすいですね。
そしてその意図を伝えて、応えてくださった素晴らしい講師の皆様・・濃い内容の講義に感謝しかありません。

自分の企画構想以上に講義内容が充実して、受講生が食い入るように聞き入っているのを見ると、後ろでついニマニマしてしまいます。
ついでに、先生方の講義の技術というか、人を引き付ける手法や技術をちょっとでも盗もうと思ったりして・・。
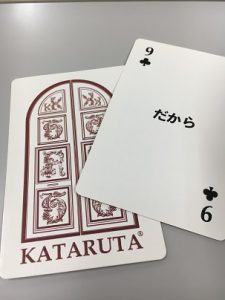
学習する人たちのレディネス(準備段階)は様々ですが、共通するのは組織の理念や使命を理解して、現場でひとりひとりが良いケアを実践することに尽きます。
そのために知っていてほしい知識は何か、身につけてほしいことは何か、プラス学ぶ楽しさや交流することで得られるものを体感してもらいたい。
そして「よし、元気もらった!明日からも頑張る」って思って帰ってもらいたい。
できれば「お、なんかちょっと変わったね。最近いい感じだね」と周りが気付くようになるといいなと思います。
だから事後レポートは「明日から私は何をする?」というのがテーマになっています。

それぞれの上役の方にはぜひともそこのところをしっかり読んでいただいて、それをテーマに対話をしてもらいたいなあと思います。
受講生が学びから何を実践しようと決心したのか、実際やってみてどうだったのか、が話に上って初めて研修が完成するのだと思います。
アンケートには
「管理者として行うべきことが、行動レベルで認識できた。業務に行き詰っている中で、とてもよいリフレッシュになった」
「グループ間の顔の見える交流はとても大切だと思いました」
「とても身にしみた意見や講義、もう少し早く参加する機会がいただけたら、目標管理や労務管理を深く考え実践できたのではと感じています」
などと書かれており、企画者冥利に尽きたのでした。
今日もこのブログにきていただきありがとうございます。
えーと、自画自賛てやつです。図々しいですね。
SNSで誰でもできることを、地道に継続すると決めた!(下)
「ソーシャルメディア塾」に通ってわかったことは、ブログを書き、それをSNS(フェイスブックやツイッターなど)と連動させることで、自分の人柄や考え方を表現し、発信することの大事さです。
普段の仕事の様子、お客様(私の場合だと患者さん)に対するサービスについてや、単純に自分の好きなことなどを「誰かのために」発信して、それを継続することが大事だと何度も言われました。
ホームページを作って、ブログのスペースを作り、何回か書いてみて反応があんまりなくてやめてしまう人も多いそうです。
またFB(フェイスブック)も、自分が投稿するだけじゃなく、友達の投稿にも「イイね」をつけ、コメントを発信してくださいと細かい指示の宿題が出されました。
そしてこれらはそんなに簡単に効果は出ないから、3年は続ける気持ちでやってみましょうと言われました。

院長と事務長も協力的なのがありがたい♡
なので、私は自分のルールを決めたのです。
ブログを読んでもらいたいのは、未来に一緒に働く看護師さん。
FBは一日1回投稿する。
友達への「イイね」は出来る限りつける。
コメントは心を動かされたらすぐ書く。
ブログは週に1回投稿する。
それらを3年続けてどんな効果が生まれるか、実験しようと。
まずは信じて素直にやってみる。

[楽しいことを発信するのが楽しい]
で、もうすぐ始めてから1年です。
ブログのネタは病院の中にいくらでもあるんですが、文章表現が・・・公開してから後悔することも(あ、ダジャレに・・)。
とりあえず上手い・下手は置いといて(汗)、今は場数を稼ぐことに専念し、いずれ見えてくるものがあるだろうと思っています。
おかげさまで看護部ホームページは訪問者12522人、総閲覧数19051人(平成29年9月16日現在)となり、就職の面接では「ブログを読んでいます」と言っていただけることが増えてきました。
ありがたいことです。
ウレシイのは、ブログを読んでてくれる方と面接すると、私は初対面ですが相手の方は私のことをなんだかよく知ってて下さるので、院内を案内してても「ああ、これがあの飾り付けなんですか」とか「このトマトの話が大好きです」などと言っていただけることなのです。
つまり初対面であっても感性の部分で共感できる人が来てくれているので、私という人間の説明が省けるのです。
そういうとき、「ああ、途中で投げ出さずに続けてて良かったな」と思います。

[FBネタとしてはもう定番]
SNSで発信するって、お金もかからず誰でもできるんです。
でも顔や名前を出すことに抵抗があったり、何を書いていいのかわからなくて手を出すのが怖い、と思う人もたくさんいると思います。
大事なのは画面の向こうにいる誰かを喜ばそうとか、誰かのためになる、と思って発信することだと白藤さんは言います。
私もようやく最近そのことがわかってきました。
今日はあえて書きますが、私はこの戦略を3年続け、いわゆる紹介会社経由での看護師採用をせずに済んだなら、その分のお金を看護ケア用品や寝心地のいいマットレスや研修費に充てたいと思っています。
これを白藤さんは「誠実な下心」と言っていたような・・。違ったかな?
今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
毎週一回元気に発信できるのは、現場のみんなが頑張ってるおかげです。ありがとお~~♬
SNSで誰でもできることを、地道に継続すると決めた!(上)
先日、久しぶりに「ソーシャルメディア塾」へ行ってきました。
平成28年6月から、6回コースで開かれたこの塾は、ITとSNSによって個人と仕事を発信し、つながりによってマーケティングを行うという目的で開かれました。
それまでSNSもホームページも「見てるだけ~」の中途半端だった私ですが、当院に1月から着任し、病院のホームページに看護部サイトを作りたいと手がけ始めたところでした。
私どもの病院は小規模ですから、はっきりいってあまりリクルートにお金はかけられません。
大規模な病院説明会への出店や、豪華なパンフレット・ノベルティグッズなどもちょっと・・いや対象者も違うし大病院とは違って一時に大量採用するわけではないのでね。
さて、じゃあどういう戦略でいこうか・・と考えていた時に 白藤沙織さんのことを知り、ブログやホームページを見て、ソーシャルメディア塾のことを知りました。
白藤さんは、「広告にお金をかけられない、中小企業の経営者にこれを学んでほしい」と書いていました。
http://www.websuccess.jp/jissenjyuku/
これを読んで、私は確信めいたものを感じました。
そして白藤さんのブログを過去に遡って読み、等身大で書かれた内容から、この人は(会ったことはないけど)信頼できる人だ、という風に思いました。数日後、私はホームページから塾の申し込みボタンをぽちっと押しました。
受講料はけして安い金額ではないし、病院から頼まれたわけでもないんですが、自分の中に「あ、これやってみたい。勇気と根気がいりそうだけど、試してみたい」という気持が湧いてきました。
そして入塾。
塾生は少人数で、ひとりひとりの仕事も背景も違います。講師の白藤さんと、スタッフの方たちがアットホームな感じで気さくに対応してくれて、緊張もほぐれました。
そのころすでに看護部のホームページを制作しかかっていたんですが、その時の発想は言って見ると「ありきたり」なホームページでした。いわゆるきれい目のモデルさんの写真を使ったもので、ちょっとよそよそしいというか、現実的じゃないというか。
白藤さんのアドバイスを受けて、私はモデルさんの写真をやめ、働く職員のイキイキした表情を載せることにしました。
できればひとりひとりのエピソードも載せたい・・今仕事を探している看護師さんに、ここで働きたいと思ってもらうためには、仲間になる人たちがどんなに親しみやすいかを表現したい。そう思うようになったのです。
それで一人一人の承諾を得て、写真を撮りエピソードを加えました。職場の写真も同じように、みんなのイキイキした顔が伝わるように。
11月にようやくホームページが完成し、さてそこからが私の本当のスタートとなりました。(つづく)




