マネジメント
アコガレの、勝原裕美子さんの講演を聞いてきました!
8/5(土)に、私のあこがれの勝原裕美子さんの講演に出かけてきました。
「キャリア開発を考える」というテーマで、市立札幌病院で行われました。
友人に誘ってもらって、外部の人間なのに一番いい席をget(笑)。

今年の春ごろ、勝原さんの亡くなられたお父様が夢に出てきて、「これまでの事、どれか一つでも欠けていたら、今のおまえはない。まだ終わっていない。お前の人生はこれからや」と声をかけられたのだそうです。
夢から覚めた勝原さんはすぐにその言葉を書き留めて、おそらくなんどもその言葉を噛みしめ、ご自分のキャリアを振り返り、20年前に今の仕事や生活を想像できていたか?想像通りでないなら、何がそうさせたのか?を自問したといいます。
こんな風に導入が始まり、看護師になる前から定年後まで、段階的に看護職が進んできたプロセスをたどりながら、お話は進みました。
看護師には、大きな病院であれば最初に配属された部署や異動した部署によって経験を積む他、自分の興味のある分野を究めてスペシャリストになる道や、管理職に進む道など、さまざまな方向性があります。
非常に有能で人柄も素晴らしい人だけれども、家庭との両立を最優先に考えて、パートで働き続けている人も、私はたくさん知っています。
何を選ぶかは、人それぞれ、ですね。
ある友人は40歳を過ぎてから看護師を目指し、家族と離れ離れに暮らしながら免許を取得しました。働きながら50歳を過ぎてから大学~大学院へと進み、60歳を超えた今現在は非常勤で働きながらも、様々なことを学び、セカンドステージを自ら作り出そうと模索しています。そんな友人に敬意を払いつつも、次のステージに向けて何かお手伝いできないかといつも思っています。
私自身も後継者を育てて次のステージに何をするかを考え準備しなきゃと思いますし、働く職員ひとりひとりのことにももっと対話が必要だなと思いました。
勝原さんの講義は、具体的で答えたくなるような質問が随所に織り込まれ、自分の体験を思い出し、重ね合わせて聞くことができました。
最近私は、人と面談するときには、より具体的で分解された質問がすごく大事だなと思っています。
「こうしてみたら?」ではなく、その人が自ら答えを見つけて進んでいけるような問い。
しかし自分で問いを作るのは結構難しいものです。
勝原さんの資料にはたくさんのヒントが詰まっていました。
そんなことからも、わたしにとってこの講義はまた宝物のひとつになりました。


今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
ちゃっかり写真とサインといただきました。これも宝物です!

市立病院のアジサイ。素敵です。
みつけたいのは自分の強み・他人の強み
自宅のベランダでえんどう豆を育てています。
花が咲き、実をつけるようになるといつも思うことがあります。
いつも見ている位置から収穫していると、翌日違う方向から見たら昨日はまったく気づかなかったところにさやの大きい実を見つけることがあることです。

昨日あるだけ収穫したと思ったのに、葉っぱの陰にかくれていて、発見できなかった。
ほんの少し角度を変えて違う方から見たら発見できたかも知れないのに。
見落とした自分がいます。

これは人に対しても同じことが言えて、人はだいたいお互いの要求によってコミュニケートするものだけど、そこには見えない側面がいくつもあるということ。
いつも不機嫌な表情で仕事をしている上司が、家ではとても子煩悩だとか。
あるいは普段無口でいるけどイラストがとっても上手な人だとか。

ちょっとした言葉のかけ違いや感情のすれ違いで「あの人はもうだめ、嫌い」とレッテルを張ってしまうと、なかなかそこの位置からはいい側面は発見できないものです。
理解のある上司や同僚ばかりとは限らないけど、うまく行かない関係性を環境のせいや人のせいにしていると、何も発展はない。
この人のいいところは何か?
この人の得意なことは何か?
をいつも観察して考えているのだけど、見てるだけじゃわからないことも多くて。
もっと聴いて、対話しないとね。
って思う。

そうはいっても、対話ですべて解決すると言うほど、おめでたい人間でもありません。
何年もの間、廊下ですれ違っておはようと挨拶しても一度も返事をしてくれなかった人もいます。
そういう人のお葬式は、絶対に行かないと心に決めています(笑)。
お互いの強みを理解してそこに焦点を当てる働き方ができれば、「日本一幸せに働ける病院が作れる」と私は信じています。
いつもこのブログに来ていただきありがとうございます。
口で言うほどには、まだまだできてない私です。

Out of the box ! 外へ出でよ!たくさん学んでたくさん感じて、帰っておいで。
植物と関わるようになってから、思考が深まってきました。
当たり前のことですが、種から急に作物にはならないわけでして、芽が出るのをじいっと待つ時間が必要ですし、適した土壌、光、水、養分を与えて病害虫から守り、植物ごとにそれぞれ育ち方があるのだと教わっています。

同じ様な環境を与えていても、場所が変われば育ち方に差が出て、いったい何が違うのかと頭を悩ませます。
ただ風が強ければ風よけを工夫し、雨が降る前に肥料を土に混ぜ、トマトは脇芽をかく。
こうしたひと手間を加えて、きっと来週には大きくなっているはずだと信頼し、翌週背丈がぐんっと伸びていたりすると、声なき植物が期待に応えてくれたようで、かわいくてたまらないものですね。
いくつになっても興味のあることを学んで元気にのびのびと育ち、他者のために貢献できる。
仲間や上司と信頼関係で結ばれている。
強みが仕事の一部になっている。
これが私の目指す日本一幸せに働ける病院の姿です。
全ての人に公平に、必要なタイミングで水や肥料を差し出したいと思ってますが、自分の目利きがまだまだ不十分です。
ただ今年はひとり、またひとりと何人か外に出して知識の泉を浴び、他者と関わり、学ぶ喜びを感じてきてほしいと思っています。
きっとその体験が養分となって、ぐんっと背が伸びてくると思います。
そして留守を守る他のスタッフもまた、成長する機会を得ます。

「Out of the box」は私が研修で教わった言葉です。
その時はブレイン・ストーミングをしていたので、既成概念を打ち破り、自由な発想で何を言ってもいい、という意味合いで使われた言葉でした。
学びが刺激となって、海外に飛び出した人もおります。
それはその人の成長のプロセスですから、(職場としては悲しいけれども)とても喜ばしいことです。
何がきっかけになるかわかりません。誰と出会うかによっても変化しますし。
それを運命というか必然というか。
私がそういうチャンスをかつての上司からいただいたように、同じことをバトン渡ししていこうと思っています。

今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
その一歩を踏み出す勇気が大事ですね。
朝ドラ「べっぴんさん」に見るドラッカー
注!ネタバレありです。年末年始にまとめて見ようと思っている方ご注意ください。
私は「あまちゃん」の頃から、朝の連続ドラマを録画して夜見るのを楽しみにしています。
夕ご飯を食べながら、15分という時間が、ちょうどいい気分転換になっています。
「まれ」「マッサン」「あさがきた」「ととねえちゃん」。
どれも仕事での苦難と成功が物語の軸になっていて、主人公は好きなこと、得意なことを仕事にして突き進んでいきます。
物語の展開とともに、「強みを活かす」「意思決定」「貢献」「時間管理」「集中」「イノベーション」など、ピーター・ドラッカーのキーワードを思い浮かべて見るようになりました。
「べっぴんさん」の主人公、すみれの夫ノリオさんは戦争から戻ってきて「坂東営業部」(という名前の会社)の社長にならんとしていました。それはすみれの婿養子だったからで、好きとか得意とかいうことよりも、「そう決まっていたから」でした。
苦手なことを克服する?
子供のころからなにを考えているかわからず、口数が少なかったノリオさんですが、社長になるためには、人前でしゃべったり、接待では道化役をしたりということに慣れなきゃいけません。「坂東営業部」で実質的な経営者である、義姉の夫のキヨシさんから、社長になるために様々な役割を与えられます。
しかし人前でしゃべることが苦手なノリオさんは、大事な時に体調を壊したりして、どうにもうまくいきません。
ノリオさんはあまり人前に出ず、会社の中で黙々と経理の仕事をしている方が得意なのです。
一方キヨシさんは、ノリオさんを立てて、自分は参謀役になろうとしていたのですが、ノリオさんが思うようにいかないのを見ていて内心歯がゆく思っていました。
好きなこと、得意なことに集中する
上手くできないこと、好きではないことを克服しようと頑張ることは悪いことではありません。が、そこに時間をかけるよりも、得意なことや好きなことをした方が、楽しいし、成果も上がります。
ノリオさんは自分が社長という立場に不向きだと言うことを知っていました。
周りの人も薄々そう思っていましたが、養子だから、会社を継がなきゃならない、という時代だったのでしょう。
苦手克服の無理をすることで、緊張と圧迫に輪をかけました。
12月24日土曜日の放送でようやくノリオさんが勇気を出して、坂東営業部を辞めることになりました。ちょうど主人公すみれの会社で経理の人が必要だった、というあたりは都合がいいようにも思いますが、まあドラマですのでご愛嬌。
よい機会を得て、得意なことに集中する。
人の役に立ち、貢献する。
ノリオさんの人生が変わり始めます。
そしてキヨシさんはいよいよ自分の番がやってきた、というところでしょう。
これで気兼ねなく自分で会社の舵取りをできる。
こちらの商売もうまく行く予感がします。
強みを活かす
ドラッカーの本には様々な名言がありますが、中でも私はこのコトバが大好きです。
自分と人の強みを発見し、いいコト、いいトコロを探すことを続け、楽しく仕事ができる環境を作りたいと思います。
今年も一年お世話になりました。
皆様どうぞよいお年をお迎えくださいませ。
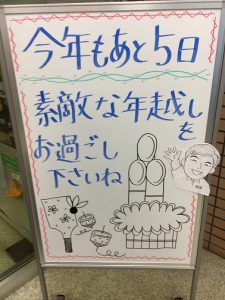
O画伯のウエルカムボードも当院の強みのひとつ
どんな手帳を使っていますか?
暮れの声を聴くころ、手帳のセミナーに行くことにしています。
きっかけは2年前、ドラッカーを学ぶ仲間から教えてもらいました。
そのころ私は手帳を使わず、スケジュール管理はYAHOOカレンダーで足りていました。
どこでも入力できるので重宝していました。のですが。
仲間から教わった手帳は「マンダラ手帳」http://www.myhou.co.jp/というもので、スケジュール管理もあるけれど、人生をどのように生きるか、を考える手帳だと言われて興味をもちました。
初心者は誰かに使い方をナビゲートしてもらった方がいいと言われ、それでセミナーに出かけることにしました。
そこではいくつかの質問を投げかけられました。
まずウィッシュリストを書く。なんでもいい。来年やりたい、と思っていることをとにかく思いつくままに書き出す。
どんな小さなことでもいい。3㌔痩せるとか、旅行に行くとか。月に一度外食をするとか。
たしか100行くらいあって、私は20個くらいしか書けないのに、周りの人は50も60もすらすらと書いていたように見えました。
そのあと、書いたウィッシュリストを8つに分類して蛍光ペンで色を塗ります。
分類は、「健康」「仕事」「お金」「家族」「社会」「人格」「学習」「遊び」の8項目になっていて、それぞれに自分で色を決めて下さいと先生に言われました。
「健康」は緑のイメージ。
「仕事」は気持ちがアガルようにピンクだな。
「お金」はいつもピーピーだから赤。
こんな感じで色を決めました。そして自分のウィッシュリストを1行ずつ分類していきました。
塗りながら気づきました。
私、ほぼピンク(仕事)の項目しかない・・・。
そのころはすべてが仕事中心でした。家に帰っても休みの日も。
週末は常に仕事を持ち帰り、何もしないまままた資料を職場に月曜日戻し、休んだ気もしないまま疲労だけが折り重なっていました。自分自身のセルフマネジメントがさっぱりできてなかったし、休みの日もON/OFFの切り替えができていませんでした。
手帳にはそのウィッシュリストを月に分けて実践行動として書き入れていきます。
月を書いたら今度は週の行動計画に落とし込みます。
計画通りに実行できたらチェックを入れます。実行したけどまだ終了していないものは翌週の計画に入れます。
毎週曜日を決めて、今週一週間のフィードバックと、翌週の行動計画を立てることを習慣化します。
私の場合大体日曜日の午後にカフェにこもってこの作業をします。
これがマンダラ手帳のだいたいのあらましです。
先生から月間の計画を立てるときに、
「今は仕事のことで一杯でも、月に一度でも「遊び」を意識的にいれましょう」
「8項目の色が必ず月のどこかに入っているようにしましょう」
と言われました。
そのころは「遊び」=オレンジ色 はほとんどなかったのですが、徐々に意識して「コンサートに行く」と書き入れました。書いて、オレンジ色を塗ると、それは楽しみな出来事としてインプットされるので、その日までにこの仕事を終わらせよう、とか、このときはすべてを忘れてうんと楽しもう、とか気構えが変わってくるのです。
それまでは「○○さんと食事」と書いても、それはその時間食事をする、ということの意味しかなかったのだけれど、オレンジ色を塗ることで「○○さんと会ってご飯を食べよう。どこで食べよう。何を話そう」と考えることが、とても楽しみになりました。
今年3年目になるその手帳に、今、来年の計画を書き出しています。
なんというか、今のウィッシュリストは感覚的にオレンジ(遊び)の方が多いかも知れません。
オレンジ(遊び)をたくさんするためにピンク(仕事)をしっかりやるよ、という気持で働いています。
というか、仕事も遊びもいっしょくたな感じかも知れません。
余白には気づいたこと、誰かが言ったいい言葉、胸が熱くなるような出来事を、なるべくすぐ書き留めることにしています。
自分に合ったいい手帳を使い、実践行動に移す、行動した結果をフィードバックすることは、時間管理になります。
私は「マンダラ手帳」を使うようになって3年、まだまだ修正の余地がたくさんあるけれど、人生の豊かさや密度の濃さは全然以前とは違うと感じています。いろいろな角度から人生を眺め、計画する思考が身に付くと、手帳の形にこだわらないような気もします。
今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
今年もあともう少しですね。
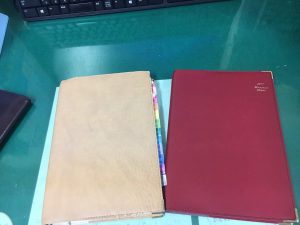
右が来年の手帳。赤にしてみました。




