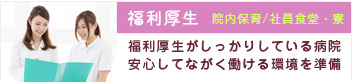あるご夫婦の姿
「お父さんがまだこの辺にいるような気がする」
Aさんが旅立ってもう数か月が経つ。
病気のため失語症になってしまったご主人の元に、奥さんは日参していた。
奥さんは一生懸命話しかけ、そばで一緒に音楽を聴き、静かに編み物をして過ごしていた。
Aさんからのことばはなくても、奥さんの献身的なケアで通じ合っているように見えた。
「ここに通うのが私の仕事なのよ」とほほ笑み、デイルームで見かける後姿は、仲睦まじい、ということばそのものだった。

Aさんの旅立ちは急なことだった。
ご家族にとってもわれわれ医療者にとっても、予期せぬことだった。
だからそのあと私たちも奥さんのことをずっと気にかけていた。
どれほどの深い悲しみに包まれているだろうかと。
一月ほど経ってソーシャルワーカーが電話をかけたときも、まだ悲しみに沈んでおられた。
それからまたしばらく時間が経った。
吹雪の合間を縫って、ようやく病院に顔を出す気持ちになられたのだ。

大切な人を亡くした場所に、足を踏み入れるのは勇気のいることに違いない。
「来てくれてありがとう」
「顔を見られて安心したわ」
「挨拶もしないでごめんなさいね」
幾人かの看護師がいたわるように声をかける。
数か月ぶりに訪れた病棟で、奥さんは懐かしそうに辺りを見回した。
そして目を細めながら、冒頭のことばをつぶやいた。
私たちも同じように感じている。
いつもお二人で寄り添って過ごした姿が、今も目に焼き付いている。
「奥さんが元気で笑って過ごせるようになるのを、ここらへんで見守っていると思いますよ」
師長が肩のあたりを手で丸く示しながらそう言って、それからやさしく奥さんをハグした。
今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
悲しみがだんだん抱えやすくなりますように。