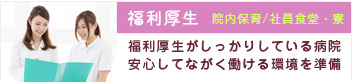「ナースのためのシシリー・ソンダーズ」を読む
いきなり言い訳っぽいですが、私はホスピスの病院に勤めていますけれども、この道の専門家というわけではありません。この病院に来てから初めてホスピスに接し、働く人たちから日々教わっています。
「グリーフ」(悲嘆)ということばも知らなかったぐらいです。
ですからその都度わかったことやすごいなあと感じたことを、ここで書いたりしています。
ただ今この本を予習中です。これは今年NPO法人「ホスピスのこころ研究所」で開催するセミナーに登壇される、小森先生が翻訳された本です。
英国人のシシリー・ソンダーズさんは、看護師・ソーシャルワーカーの資格を取った後医師の免許も取り、セント・クリストファー病院を建てられて、ホスピスの母と呼ばれる方です。
この本は医師になって2年目に看護師向けに書かれた本なのですが、その視点・洞察・表現に驚きます。
少し引用してみます。
―「彼ら(患者)は、ケアのよい技術と同様、温かさと友情を必要としていた。私たちは痛みがどんなものかを学ばなければならない。重い病気になるというのはどういうことか、仕事を辞めて人生から撤退するのはどういうことか、身体精神機能が低下することや、大切な人やいろいろな責任を失うことについても知らなければならない」
(第12章 私と共に目を覚ましていなさい)―

当院の前野総長が、緩和ケアを学びに来た学生や医療者によく言うのは、このことです。
「私たち医療者は健康で働いていて、重い病気を持った人の気持ちになろうとしてもなることはできない。ましてやがんの末期になったこともないのだ。だから患者さんひとりひとりに教えていただくしかない。このケアでよかったのかどうかを常に問い続けなければならない」と。
それからこんな一節も読んでいてこころが温まります。
―「人々がありのままに受け入れられて、安全の中でリラックスできる、良い家庭にみられる歓迎とかホスピタリティを提供できる家庭のようなホームにならなければならない。」(同)ー
これは病院全体がこうでありたいといつも願っていることです。
職員同士も家族のように、お互いを尊敬しあえるチームでなければ、患者さんに気持ちを緩めてもらうことはできないですから。
そしてここも。
―「私たちは彼ら(患者)が鞄に正しいものを詰め、大切なもので満たし、彼らの必要とする物を入れることができるようになれば、と祈るべきだと思う。ここにいる間に、彼らは人生のこの最後の時期に、自らの和解、成就、そして意味を見つけるだろう。」(同)ー
最期のときを温かく穏やかな中に包まれて旅立てますように、と願いながら。
今日もこのブログに来ていただきありがとうございます。
4月20日(土)13:00~札幌 かでる2・7で翻訳者である小森康永先生の講演があります。
お時間がある方お運びください。