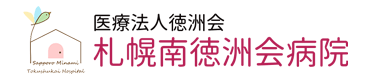昨日、秋晴れのホテルさっぽろ芸文館で、上記の記念講演会が開催されました。
1年以上前から企画をしていたのですが、ようやくこの日が来たと思いました。
今回は、3部構成で第1部は、札幌南青洲病院ホスピスの10年とホームケアクリニック札幌
の5年のあゆみをそれぞれ振り返りました。ホスピスの10年は私が担当しましたが、過去の写真
を探したり、過去にいたスタッフの写真を見たりすると、それぞれに懐かしさと時代を感じる
時間でした。10年間という時間で、ホスピスで働く人たちは随分変わりましたが、最初に作り
上げようとしたその理念はしっかりと根付いていると感じました。
第2部はアンサンブルグループ奏楽(そら)さんたちによるミニコンサートでした。その
プロデュースは、ホームケアクリニック札幌の院長の前野先生で、前野先生が選曲した音楽を
すてきなピアノやバイオリン、オーボエなどで演奏していただきました。第2部の最後は中島
みゆきの「時代」をフロアのみなさんと合唱しました。
第3部は我らホスピス医の第一人者である柏木哲夫先生の講演会でした。「ホスピスのこころ
を深める」というテーマで、いろいろな話に及びました。ホスピスケアというのは、当初は支える
ことと思っていたが、そうではなく『寄り添う』ことであることを。人は強い苦悩を与えられた時
スピリチュアルペインが覚醒してくるので、それをケアするのもホスピスケアだということ。
また、ホスピスのこころを深めるにはケアをする一人ひとりが『人間力』を高めることと話されて
いました。
この10年のあゆみに感謝し、それぞれが人間力を高めて、一歩一歩進み、さらにいいホスピスを
作っていきたいと思った記念講演会でした。