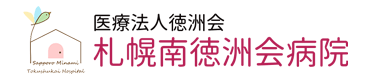3月19日の午後、道新ホールで札幌ホスピス緩和ケアネットワークの
特別講演会がありました。当初は東京の山崎章郎先生と福岡の二ノ坂
保喜先生の講演会と前野宏先生を含めた3人の鼎談の予定でしたが、
先週の大震災の影響で、山崎先生の来道がキャンセルとなり、二ノ坂
先生の講演が中心となりました。
二ノ坂先生は、地域で開業医をやっていく上で必然的に在宅ホスピス
ケアをやり始めた方で、私たちが病院の中でホスピスケアをやっている
とつい忘れがちな観点を講演の中で話してくれました。
特に我が国のホスピスの問題点は、診療報酬上、「がん」と「エイズ」
のみが対象となっていること。元々ホスピス運動はそうではなかったと
言っていたことが印象的でした。
在宅ホスピスは何も「がん」ばかりでなく、神経難病や小児の難治性疾患
も対象にしないといけないし、それが当たり前として実践していることが
すばらしいと思いました。
山崎先生の講演が中止となってしまいましたが、二ノ坂先生のお話をたっぷり
と聞けて、3時間があっという間に過ぎました。
今年もいい講演が聴けたと思いました。