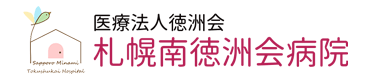みなさんは日野原重明先生をご存知でしょう。あの聖路加国際病院の理事長であり、
数々の役職を兼任されている方です。
今回、日野原先生が札幌に来る機会があり、有志が集まって日野原先生の100歳を
祝う会が催されました。当院の副理事長である前野先生からのお誘いもあり、私も
参加させて頂きました。11月21日の昼から中島公園にある由緒ある豊平館での開催
でした。日野原先生は明治44年(1911年)10月4日生まれで正確には満99歳なので
すが、数えではもう100歳になったとのことで、今回100歳のお祝いの会が開催され
ました。いつも思うのですが、少し猫背ぎみではありますが、100歳とは思えない
ぐらいしっかりしており、きちんと挨拶はされるし、みんなで「ふるさと」を合唱
したのですが、その指揮もやられました。本人は、100歳の今までは助走期間でこれ
からがスタートラインでジャンプするんだと言っていました。その気持ちは本当に
凄い。だからこんなに元気でいられるんだと思いました。
私は日野原先生の半分にも満たない年です。あそこまでは頑張れないにしても、
元気をもらった会でした。
月: 2010年11月
-
日野原先生を囲む会
-
東京出張
本日、日帰りで東京に出張してきました。 目的は徳洲会グループ1年次研修医
向けの講演会でした。
「ベッドサイドのコミュニケーション」という題目でお話しをさせてもらいました。
全国の徳洲会グループに今年の4月に入職した初期研修医は約100名で、各病院で
日々忙しい臨床を毎日こなしていますが、入職して約半年が経ち、自分たちがやって
いることを振り返ること、また全国の徳洲会の研修医同志の交流のため、今回1泊2日
で東京に集合したのでした。今回、徳洲会の研修委員会から講演の依頼があり、当直
の合間に日帰りしてきました。
内容は、がんの告知などの悪い知らせの伝え方(Breaking Bad News)の手順、私たち
が普段ホスピスで実践している患者さんとのコミュニケーション技術としてのベッド
サイドに座る、聴くについて話しました。研修医向けに話しながら、また自分もきちん
と実践できているのかと振り返る機会になりました。
今回の講演を聞いて、来年ホスピス研修に来てくれる研修医が増えるといいなと思って
札幌に戻ってきました。 -
✴︎
✴︎ 病院関連病院の看板
みなさん、こんにちは。しばらく更新していなくて申し訳ありません。
病院のニュースです。以前から当院に初めて来る方が当院の場所がわかりにくい
と指摘がありました。病院の場所が下を走っている旧国道から少し上にあるために車で
来る方は見逃して通り過ぎることが多いのです。
なんとか看板を付けなくてはということで、ようやく向かいのケアタウン徳洲会
札幌南の敷地をお借りして、病院案内の看板ができました。
今朝から工事が始まり、午後には立派に立っていました。
これで患者さんが増える。変な確信を持ってしまいました。
-
✴︎
✴︎ ホスピス関連日本死の臨床研究会年次大会(盛岡)
11月6,7日の2日間盛岡で日本死の臨床研究会の第34回年次大会が開催され、
参加してきました。
約30年前、あまりにも医療の中に死が閉じ込められ、みんなが苦しいまま病院で
亡くなっていく現実に、これはなんとかしないといけないと有志が立ち上がり、
1977年に日本死の臨床研究会というものが出来たのです。日本のホスピス・緩和ケア
の領域では一番最初にできた集まりで、また死を取り上げているというとても
ユニークな研究会です。わたしもこの緩和ケアに携わり始めてから毎年参加するよう
になっています。
最近は、緩和ケアが普及が著しいですが、あえてこの研究会は緩和ケアの普及自体が
生を支えすぎて人間のいつかは死を迎える現実を遠ざけてしまっているということを
危惧していると訴え続けています。今回の年次大会は東北地区で開催されたこともあり、テーマは「地域で看取る」。
どのようにして人生の終末期を地域の中で支えていくべきか、活発な議論がありました。
私は事情で、一日目しか参加しなかったのですが、昼のセミナーで聞いた小笠原内科の
小笠原文雄先生のお話がとても印象的でした。もともと循環器内科医でありながら、
開業したので在宅を始めてしまい、色々な患者さんとの出会いからいつの間にか
在宅緩和ケア医になってしまったとのこと。なんと在宅の死亡率が90%を超えている!
そこには、患者さん本人の家に帰りたいという気持ち。それを支える家族、スタッフの
がんばりがあることをセミナーを聞いてヒシヒシと感じました。
我々ホスピス病棟を運営しているものにとってもとても刺激的な内容で、家の力には
勝てないけれど、ホスピスマインドだけは常に大切にして患者さん・家族に関わることが
原点と思いました。