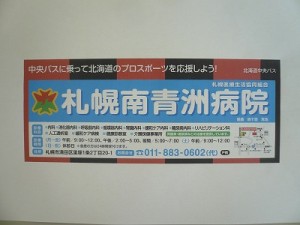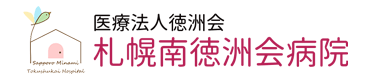(長くなり、続きです)
2日目(9月7日)の朝3時頃、医局のソファの上でふと目が覚めました。ちょうど地震発生から
24時間が経過していますが、まだ外は暗く電気の復旧はしていませんでした。この時期の札幌の
日の出は5時過ぎ。4時頃になれば外は明るくなってきます。ですからまだまっ暗な状態。病院内
をぐるっと回りましたが、大きな異常は無くてほっとしました。自家発電による電気のお陰で、
病棟のナースステーションの蛍光灯はとても明るいですが、病室や廊下・階段はまっ暗な状態。
手持ちのライトで床を照らしながらの移動しました。
1階のロビーに降りると、事務長やその他の職員が長椅子の上で寝ていました。起こさないように
そっと側を通りました。
もう一度仮眠を取り、起きたのが5時過ぎ。外は明るくなっていました。病院の方は特に変化が
無かったので、一度液状化現象が起きたところを見に行っておこうと思い、外に出かけました。
病院の裏側から歩いて行くと3分ほどでその現場に着きました。以前、訪問に行っていた患者さん
の家の隣の家のところから液状化が起こって、アスファルトが波打っていました。ちょっと先には
テレビでも写っていた紺の車が泥の中にはまっていました。来た道を引き返し、別の方へ歩いて
行くと夜の間ずっと復旧工事をしている人たちがいました。
これ以上は病院を離れてはいけないと思い、再び病院に戻りました。
地震発生から翌朝を迎えていました。自分の自宅は大丈夫と妻から連絡はもらっていましたが、
一度見に行った方がいいと考え、事務長に伝え自宅へ戻りました。自転車で自宅へ往復。一部の
信号は点灯していましたが、ほとんどはついていませでした。大きな交差点では警察官が交通整理
をしてくれたお陰で安心して渡ることができました。
自宅では、家族が無事一夜を過ごし、保管してた水や残った食べ物を食べていて、特に困っている
様子はなかったようです。子供たちは学校が休みになったため、手持ち無沙汰なようでした。
自宅で朝ご飯を食べ、少しだけ鋭気を養い再び病院へ。
朝8時前から再び1階のロビーに職員が集合し、今日からのスケジュールが始まりました。
朝6時の時点で電源の復旧の目途はなし。まだ断水も継続していました。車の燃料は近くのガソ
リンスタンドのご厚意により当院の車に優先的に配給してもらいました。
自家発電の方は、いくつかの方面から確保ができ、まず夕方までは軽油が確保できました。
それよりも電源の復旧に関しては、各方面からのサポートで2日目の昼過ぎに電源車が確保でき
そうな連絡がありとてもうれしい知らせとなりました。もし電源車が到着すれば、ほぼ電気の
心配が無くなり、通常の通り電子カルテなどが使える状態になるとのことでした。
また、札幌市水道局も断水が続くと受水槽の水が足りなくなることを伝えたところ、給水車を派遣
してくれました。
実は、1日目の夜からすぐ近くにあるガソリンスタンドとコンビニの電気がついており、病院の
後ろの家の電気もついていたので、もうすぐ電気が来るだろうと淡い期待をしていたのですが、
全然電気が来ません。次の日の昼近くになってもまったく電源の復旧の気配はありませんでした。
ラジオからの情報では、苫東厚真の発電所がダウンし、全道が停電していて、順次発電所を稼働
しているけれど全部復旧するにはかなりの時間がかかりそうということはわかっていました。
朝の会議で、2日目の診療は基本的には制限しながら、歩いてくる患者さんの診療は継続(電気
はないので、検査などはできないが、投薬はできるので、その旨を話して受付とした)しました。
救急受け入れは基本的には断りましたが、通院患者さんで在宅酸素が必要な患者さんは2名入院と
しました。それ以降は入院も中止としました。
透析に関しては9月7日の透析は中止。明日以降に出来ることを見越して、中止としました。
そこまでを決めた後は、各自が持ち場の仕事をこなして行きました。私はラジオから流れる情報を
常に収集していました。
午前中は、予想以上に外来患者さんが来院され、20名以上が診察を受けました。
午後になり、電源車が来るという情報も来たのですが、結局まだ動けないということで、夕方
まで持ち越しになりました。
燃料の方は、順次確保することができ、自衛隊からのサポートがありドラム缶1缶を置いていって
くれたお陰で、翌朝まで自家発電の燃料の心配はなくなりました。
そうして時間が過ぎ、日が暮れ1階のロビーがどんどん暗くなっていきました。停電が続いたまま
2日目の夜を迎えました。
17時過ぎに1階のロビーに全員が集合。病棟の食事を配膳した後は、ほぼ急を要する仕事は
無くなったため、夜に向けたの体制を整え、明日の準備のため必要な人以外は各自自宅待機と
なりました。
残った人は、電源車がもし来て電源が復旧したときに備えて待機。電源復旧の際は、電子カルテ
のサーバーを立ち上げて、動作確認。また、翌日からの透析が出来るように準備するための
メンバーと数名のサポートの人間のみが残りました。
20時を過ぎても、電源車はやってきませんでした。もう今日もこのままかなと思っていたときに
いきなり「バン、バン、バン」と1階のロビーの電気が点灯しました。
「え?え?え?」「電源復旧???」 ようやく電気が戻りました。「本当だよね? 嘘じゃ
ないよね。また切れる?」などと言いながら、もう大丈夫でしょうと思い、思わず拍手を
してしまいました。
それからはすぐに電子カルテのサーバーを立ち上げてもらいました。透析のスタッフには
明日からの透析の準備を始めてもらいました。
22時にはサーバーが完全に復旧し、電子カルテの動作を確認しました。そして23時には透析の
準備もOKという連絡をもらいました。
ほぼ明日からの診療はできると判断しました。
23時30分すぎ、透析責任者の副院長と一緒に家に帰りました。地震発生の6日の朝3時過ぎから
約44時間が経過してました。まだ水道の断水のことは残っていましたが、電気が戻り明日から
通常に戻ると思い、ほっとして家に向かいました。
病院から帰る道、もうほとんどの信号と電灯がついていました。ほぼ電気が元通りになったと
思いました。自宅前の電灯もついているので大丈夫と思い、家に入ったところ、真っ暗。
「ん?」 声をかけても誰も起きません。それに家の電気は何もついていない。何?
あ!ブレーカー落としている!と思いました。まあ、偉いですね。
ブレーカーを入れると、家の電気が点灯しました。冷蔵庫のスイッチも入りました。
ほっとして、眠りにつきました。
(以上、長い文章でしたが、電源復旧までの小さなドラマでした。)