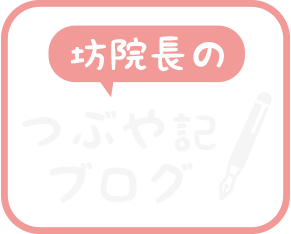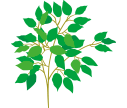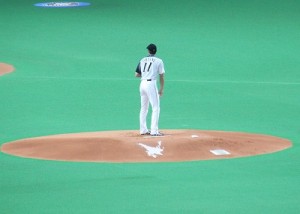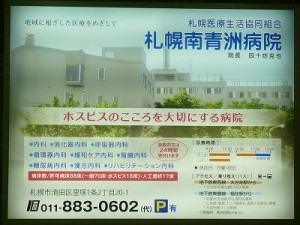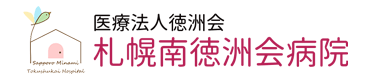みなさん、こんにちは。2月に入りましたが、寒い日が続いています。今年は、2月に
入っても寒い日が続いていますね。ちょうどさっぽろ雪まつりの季節で、雪像が融けたり
する心配がなくてよかったですね。
さて、高齢化社会の進行に伴い認知症の患者さんが増えています。外来をやっていても
確実に高齢者の数は増えているし、また認知症を抱えて入院する方も増えています。
私たちも認知症=アルツハイマーと思っているところがあり、認知症の患者さんが
来ると扱いに困ってしまい、どうしても精神科に紹介してしまうことが多いです。
アルツハイマー型認知症にはアリセプトという効果のある薬があり、10年以上前から
使われています。これは認知症を治すというよりは進行を遅らせる薬で、私たちも
アリセプトを飲んでいる患者さんが穏やかに過ごしているのをよく見かけます。
ところが、すべての認知症に方にアリセプトが効果があるとは言えず、逆効果になる
ことがあるそうです。それに気づいたのが、名古屋フォレストクリニックの河野先生
だったそうで、「コウノメソッド」というものを開発したそうです。こころある医師なら
この「コウノメソッド」を勉強して、認知症に苦しむ患者さん、家族を助けようというもの
だそうです。
その「コウノメソッド」を当院の田村先生が約1年間独自で勉強をして、実際に当院の
外来患者さんに実践してみようと考えています。
そこで、当院の職員にもその「コウノメソッド」を理解してもらうために、2月に入って
から勉強会を始めました。2月3日に第一回の勉強会が開催されました。なるべくたくさん
の職員に参加してもらうため、週に2回勉強会を開催して、同じ内容の講義をしてくれる
ことになりました。
下はその時の風景です。当院のスタッフだけでなく、関連施設の職員なんかも参加して
くれて、やなり認知症は大事なトピックであること感じました。