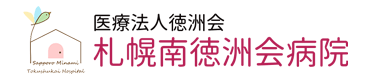秋晴れの東京に上記試験を受けに行ってきました。日本プライマリ・ケア連合学会が
主催する認定試験です。今回を含めて計3回の移行措置に伴う試験です。
何年か前より厚労省を中心に専門医のあり方に関して協議がなされていました。
2004年(平成16年)より新臨床研修制度が始まり、医学部を出る全ての医師は
厚労省が指定する研修指定病院での2年間の研修が義務づけられました。
そのために若い先生達が大学の医局に残らず、市中の有名研修病院に集まるように
なり、地域医療が崩壊したと言われました。
しかし、現実はそこが問題ではなかったのです。確かに若い先生(2年以内)達が
都市部で研修するようになったのですが、問題のその後の医師達の行き先が問題でした。
2年の臨床研修が終わった後は、やはり多くの人たちが専門医を目指したのでした。
例えば、循環器専門医、耳鼻科医、麻酔科医など、それぞれが興味を示す科を指向した
のでした。そうすれば、やはり地域で働こうという医師は少数派でした。国も医師会も
そんなことは関知していません。まったくの自由意志でみんなが動くのです。
予想通り、地域医療は崩壊へと進みました。新臨床研修制度が地域医療の崩壊の原因だと
いう指摘は誤りでした。やはり医師を適正に配置する仕組みが必要であると厚労省も
とうとう気づきました。
それが、厚労省の専門医のあり方の協議会で浮き彫りになったことでした。そうすると現在
行われている学会主導の専門医の養成には問題があるということになりました。
どこかの第3者機関が適正な専門医をまとめ上げる必要があるとの認識です。そして
現在、いろいろな専門医がいますが、医療に必要な専門医を決める必要があるとなりま
した。そして、足りない専門医として、地域を支えるプライマリケア医であるという
ことでした。そして19番目の専門医として「総合診療医」という専門医が創設される
ことになりました。その専門医を担うのが「プライマリ・ケア連合学会」なのです。
その専門医を増やすため、移行措置として「プライマリ・ケア認定医」試験が行われ、
受けてきました。記述試験で120分。久しぶりにドキドキして目一杯時間を使って
試験を受けてきました。発表は来年2月頃だそうです。合格したらブログで報告します。